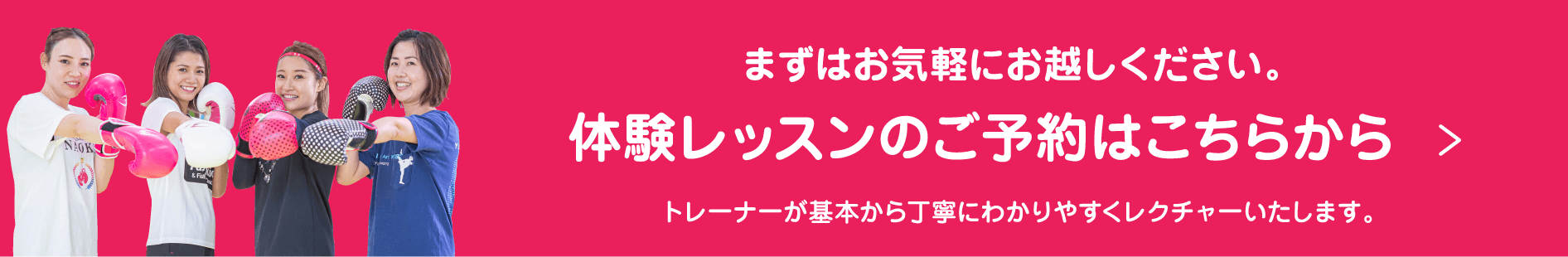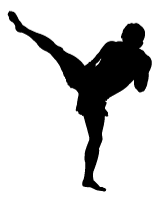 「働きアリの法則」と言われる「2-6-2」のフォーメーションは、それぞれのテンションの割合へと転換
「働きアリの法則」と言われる「2-6-2」のフォーメーションは、それぞれのテンションの割合へと転換
2025.06.30

「働きアリの法則」って、働きアリに関する法則で「2-6-2の法則」とも言うみたいです。
働きアリのうち、よく働く2割のアリが8割の食料を集めてくる。
よく働いているアリと、普通に働いている(時々サボっている)アリと、結構サボっているアリの割合が、2:6:2になる。
よく働いているアリ2割をそこから間引くと、残りの8割の中の2割がよく働くアリになり全体としてはまた2:6:2の分担になる。
そういうことじゃったら!って、よく働いているアリだけを集めたとしても、その一部がサボり始め、やはり2:6:2に分かれる。
そうかと思えば、サボっているアリだけを集めると、その一部が働きだし、やはり2:6:2に分かれるっていう話。

人間も同じじゃないのか!?って思った織田信長。
部下を率いる軍を持つことでそんな生物の決まり(法則)を知った信長は、思考した上で指摘し動かすことができる自分を見せつけるべく張り切るも、周囲の心の動きから始まる裏切りなどに頭を悩ませたみたい。。。
こんな法則に関しては、スポーツシーンでやビジネスシーンでも用いられる事が多いとのこと。
優弥道場では「当たり前のことを大切に」って「かっこいい行動を心がけよう」って話してます。
そうやって「全員が全員を引っ張るんじゃーっ!」「全員が主役じゃーっ!」なんて呼びかけています。
そんな毎日は考えることだらけですが「悩み」とは違いますし、うまくいかせなければ向上していない!という考えもありません。
「スムーズにいかせよう」「思い通りにいかせよう」そんな感覚がないのは…思うことがないわけではなく、それぞれのオリジナルの素敵な部分を知りたいから「既定の型にはめてしまうこと」「優弥色に染めてしまうこと」を「勿体無いと感じている」が正しい表現ですね。(確実にいらんことした時は言うけどね)
なのでスタッフや生徒に対して「部下」とか「弟子」とかそんな呼び方をしようとする感覚すらないのです。実際もそんな呼び方もしていませんが一般的な構図としての見方から周りがそう表すことに関して文句があるわけではないんですけどね。

優弥道場のみんなには「空手を通じて感じることや学ぶことというのは空手以外の時に役に立つ」と伝えています。空手の時間を通じて、自分と向き合うってことを学びながら、みんなで頑張る雰囲気の存在を知ることで、ますます学んでいくようになるみんな。
「人を引っ張る」なんてことも任せてみると、その時にまとうべき雰囲気なんかをそれぞれが創ります。
まとめるために声を出す?それぞれでやってもらえるように見本になる?理解できるように手を取って教える?そうやって考えて工夫を凝らして自分のカラダを使うのです。
「人に引っ張られる」なんていう感覚は体感しながら学ぶ他ないわけで、そんな経験を周りのおかげで気持ちよく積んでいくみんな。
組み手やミットでは、相手を叩いた時の手の衝撃と自分の気持ちと相手の表情!相手に叩かれた時の自分のお腹のヘコミ具合と自分の気持ちと相手の表情!そんな手応えや表情から感情を類推したりすることなんかも、自然と学んでいきます。。。
自分がやられて嫌なことを相手にやる格闘技と、自分がやられて嫌なことは相手にはやらない日常の完成です。

「2-6-2の法則」はグループ内で生じる比較数とだけはせず、それぞれの生きるテンションに照らし合わせるものだと考えたい。
生徒は空手の稽古時間を「2-6-2の法則」で過ごしている気がします。
2 最高に張り切る
6 楽しくはしゃぐ
2 心をゆるめ落ち着く
たぶん今日という「1日」もこのテンションの割合で過ごしていて、1週間も1ヶ月も1年も「2-6-2の法則」を自然と用いて過ごしているんだと思います。
「これは人間にとって心地良いリズムである」ということなんだと思います。
心地よいことは「快良いこと」「不快」でない「快」。だから「続く」という心理だと思うんですよね。。。
一つ前のブログに書いたように、僕のこどものころの夢はおとなになる事でした。
わからないことを尋ねるたびに、たくさんの気づきをくれる「おとな」
“自分がわからないことがわかるおとなを尊敬”そんな意識で生きていくうちに、同級生でも年下でも、何かを尋ねた際には”それぞれの答えをくれること”を僕は知っていきます。。。
そうやって人を好きになってきた僕は、好きな人たちと好きなように過ごさせてもらう時を今も生きています。
昔からあるそんな日々には感謝しかなくてずっと幸せで、、、
常に好きな人と好きなことをさせてもらって生きてきたうえでもう一つの夢だった空手の先生になった今も
2 一生懸命張り切るフリ(先生なので行き過ぎないように)
6 一生懸命はしゃぐフリ(先生なので行き過ぎないように)
2 一生懸命落ち着いたフリ(先生なので行き過ぎないように)
と、好きなことを好きな人と好きなように一生懸命表現させてもらっている今。
誰よりも幸せなんだという自負があります。
これは絶対そう!だからみんなに伝えていきたい♡という思い。

やっぱり「嫌い」の感覚はストレスなので、嫌いの感覚すらも「なんで?」に落とし込んでみて、じゃぁこうやったらどう?なんて「嫌い」に盛り付けをほどこし「好き」へとアレンジする「考え方」のクセづけは大切。
身の回りのすべてを「好き」と「楽しい」で埋め尽くしていけば「幸せ」になれる。だから、楽しいんだけど「怖い」や「痛い」が隣り合わせの空手は最高。
背中合わせにある「闘争心」と「逃走心」に向き合いながら逃げながら本気で考えさせられるからこそ学べることから素敵が育つ!
成長していくためには必須の”やる気スイッチ”これは他人が推せるものではなく自分自身で推してもらう自分の内側にあるボタン。そのスイッチの押し方を薦めてあげやすいから。スイッチを押せたその子を褒めてあげやすいから。その子が自分を好きになれるから。かっこいい!の心がたくさん育つ!
こんな「素敵」の感覚は、なくても死ぬわけではありませんが、生きていく上で「自分をより幸せにしてくれる考え方」となっていき自分を幸せにしてくれます。

これからも、本気で寄り添うことを含め「当たり前のことを大切にしながらその当たり前の質を上げていくこと」を基本軸とし、引き続き楽しんでいきたいと思っています。
好きで楽しいことなんて、おとなもこどももほうっておいても時間を忘れてやりますから!
自分を含む全てを好きになると愛情深くなり、人間臭くなり、生きていく事がもっともっと楽しくなっていきますよ♡
たぶん!

「信長の原則」「働きアリの法則」と言われて世に出ている「2-6-2の法則」を参考に
優弥道場では「2-6-2」のフォーメーションをそれぞれのテンションの割合へと転換して考え直すことで、全てを自分磨きの学びとして本気で寄り添い精進してみます!という確かではないことへの意気込みを長ったらしく書いただけの心苦しいだけの投稿
関連記事